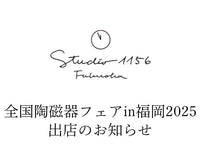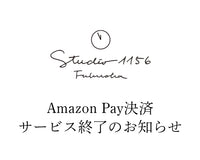「やちむん」の里へ
沖縄の焼き物「やちむん」。その素朴であたたかみのある風合いに魅せられ、全国的にも人気が高まっています。
陶磁器セレクトショップ"Studio1156(スタジオイイコロ)"でも、やちむんを取り扱いたいという思いを胸に、今回、現地沖縄を訪れました。
自分たちの目で見て、触れて、感じて、「どんなやちむんを扱いたいか」「Studio1156に合う器とは何か」を確かめることが目的でした。
いくつかの窯元を巡るなかで、心に残ったこと、驚いたこと、考えさせられたことがたくさんありました。
今回は、旅の記録とともに、やちむんの購入方法や選び方、今の現地の空気感をここに残しておこうと思います。
初めてやちむんを知る方も、すでにファンの方も、器との出会いを楽しむヒントになれば幸いです。
やちむんって何?
やちむんとは
「やちむん」とは、沖縄の方言で「焼き物(やきもの)」を意味します。代表的なやちむんには、読谷山焼、壺屋焼があります。全体的にあたたかみのある、ぽってりとしたフォルムが特徴で、「呉須」・「飴」・「黒」・「緑(オーグスヤー)」など、沖縄ならではの鮮やかな色彩で彩られた器が多く見られます。指描き(ゆびがき)模様や唐草文、魚文など、どこか民藝的な素朴さも、やちむんならではの魅力です。
やちむんってどこで焼かれている?
主な産地は、那覇から車で1時間ほど北上した場所にある読谷(よみたん)村の「やちむんの里」。こちらには現在19軒の工房が集まっており、やちむんの中心地として知られています。その一方で、旅行者にとっては足を運びやすい那覇市壺屋にある「やちむん通り」や、石垣島をはじめとした離島にも多くの窯元が点在しており、沖縄県全体で見ると、現在稼働中のやちむんの窯元は大小あわせて約70〜100軒ほどありそうです。
料理との相性
「やちむんは和食用?洋食の器?」という声も聞こえてきそうですが、不思議とジャンルレスで、和食・中華・沖縄料理・洋食など、どんなスタイルの料理にも自然に溶け込む器です。ぽってりとしたフォルムや手描きのあたたかみが、料理そのものの個性を邪魔せず、程よく引き立ててくれます。
有田焼や美濃焼など他産地との違い
型成形やパッド印刷、転写技法などで規格を揃え安定した量産が可能な有田焼や美濃焼と違い、やちむんは一つひとつロクロやタタラで成形され、絵付けもすべて手描きです。焼成にはガス窯や電気窯も多く使われていますが、昔ながらの登り窯で焼かれるやちむんも少なくありません。そのため、器によってはどうしても個体差が大きく出ることがあります。
でも、やちむんの魅力はまさにそこ。「完璧に揃った均一さ」ではなく、「個性」「あたたかさ」「土と手仕事のゆらぎ」にこそ、美しさがあります。国内のやきもの産地にはそれぞれ得意不得意があります。
当店、陶磁器セレクトショップ"Studio1156(スタジオイイコロ)"では、そうした“個性の違い”が補い合えるように、他産地の器もバランスよくセレクトするよう心がけています。
発掘ストーリー/仕入れ裏話
やちむんの現状
やちむんの作り手のもとを正式に訪ねるのは、今回が初めてでした。だからこそ、まずは現地の現状を、自分の目でしっかり見てみたい——そんな思いがありました。とはいえ、今回の旅の一番の目的は、やちむんの仕入れです。目標としていたのは、3寸〜5寸の小皿、小鉢や小丼、マカイ(茶碗)、箸置きなどの小物たち。
夏の終わりには、いくつかの窯元さんのお品を集めて、当店でやちむん特集が組めたらいいな…そんな構想を胸に抱いての出発でした。
が、しかし——。
仕入れの現状や入荷の難しさ
今回の旅は、正直とても苦しいものとなりました。理由はただ一つ。
「仕入れができない」という現実に直面したからです。
有田焼や美濃焼のように、窯元が作り問屋が流通を担う“産業としての体制”が整っている地域とは異なり、やちむんの多くの作り手たちは、柳宗悦や濱田庄司らが提唱した「用の美・民藝」の思想を今なお大切に守っています。
さらに今まさに、空前のやちむんブーム。
「物理的に生産が追いつかない」というのも、現地で実感したリアルな状況でした。もちろん私たちとしても、器を丁寧に扱い、お客様に誠実に届けたいという思いは変わりません。しかし、作り手に無理をお願いするようなことはしたくない。その思いもまた、揺るぎません。この葛藤こそが、今回の旅で最も大きなテーマだったように思います。
そんな中でも、まずは一つの窯元さんとご縁をいただけそうなので、当店でも仕入れが叶いました。本当にありがたく、嬉しいかぎりです。沖縄の風土と人の手が生んだ器たちを、早く皆さまにお披露目できるよう、店頭への準備を進めてまいります。
なぜ人気が高まっているのか?
近年、やちむん人気が急上昇したきっかけとして、まず外せないのが BEAMSとのコラボではないでしょうか。2017年に「OKINAWAN MARKET(オキナワンマーケット)」と銘打ち、それまでやちむんを知らなかった層にも広く認知され、一躍、全国区の存在となりました。それに伴い、SNSを通じた情報拡散も相まって、引いては海外からの需要も徐々に増加。セレクトショップや百貨店の積極的な取り扱いも一気に増えました。
コロナ禍がもたらした変化と試練
そんな折、突如として訪れたのが、コロナ禍。観光客が激減し、お店への来客もぱったり。加えて、ホテルや飲食店からのオーダーも止まり、ついには窯の稼働すらストップする状況に陥りました。そこで、多くの窯元が新たな販路=EC(オンライン販売)へと舵を切る動きが見られるようになったのだと思います。
EC販売では、「画像と大きく異なる」「イメージと違った」「返品したい」といった声が少なからず寄せられ、作り手たちは戸惑い、対応に苦慮されたことでしょう。やちむんのように、絵柄や形にゆらぎがあり、実際に手にとって「どれが好きか」「どれがしっくりくるか」と吟味しながら選ぶ器にとって、“実物を見られない”コロナ禍の影響は、やはり大きかったのではないかと感じました。
そして、今
そして今、すっかり観光も戻り、インバウンド需要も再び高まるなかで、リアルとECがバランスよく共存する時代が戻ってきたのではないかと感じています。“流行”が訪れ、コロナ禍を経て、そして現在のインバウンドの波——。
やちむんの世界もまた、その流れの中で少しずつ姿を変えています。観光客向けに楽しく自由な作品を生み出す窯元、新しい美意識で「ミニマル」「マット釉薬」「北欧風」などのモダンな器を手がける若手作家や女性作家たち。その一方で、民藝の精神を丁寧に守り続けている窯元もなお健在です。
今回の旅では、そうしたさまざまな想いと方向性が共存する現場の姿を、まざまざと見せつけられたように思います。
やちむんの購入方法まとめ
1.やっぱり現地購入がいちばんのおすすめ
沖縄を訪れる機会があるなら、ぜひ窯元や工房に直接足を運んでみてください。写真やSNSでは伝わらない手ざわりや重さ、釉薬の発色に出会えます。
- ✔ 同一品も最も安価であることが多い
- ✔ 作り手と話しながら選べる楽しさ
- ✔ 一点ものとの偶然の出会い
また、年に数回開かれる「壺屋陶器まつり」「読谷やちむん市」などの大型陶器市もおすすめです。40社以上が集まり、通常は非公開の作品や掘り出し物も出ることも。また現地ホテルの売店にはセンスよく選ばれた器が並んでいます。観光とあわせて買い物ができる気軽さも良いですね。
2.県外の移動販売・ポップアップイベント
最近では、窯元自らが東京や大阪、名古屋などで期間限定販売(ポップアップ)を行うケースも増えているようです。
- 作り手と直接会って話ができる
- 現地へ行かずに「一期一会」を楽しめる
- 人気窯元は整理券や事前予約が必要なことも
3.窯元のSNS・オンラインショップで購入
多くの窯元がInstagramやECサイトを通じて作品を紹介・販売しています。
- 一点ごとに写真撮影されていて、状態も分かりやすい
- 質感や色味のイメージ違いが起こりにくい
- メルカリなど個人取引でもやちむんは多く出品されている
4.百貨店やセレクトショップ・ギャラリーで探す
やちむんの人気が高まる中で、全国の百貨店や個性的なセレクトショップ・ギャラリーでも取り扱いが広がっています。
- BEAMS、CLASKA、TODAY’S SPECIALなど大手雑貨店には在庫がある可能性が高い
- 店員さんの知識が豊富で、窯元の背景なども教えてもらえる
- 高品質かつ、流通管理された安心感あり
5.Studio1156で購入する
当店でもやちむんの取り扱いを開始しました。以下よりご覧いただけます。
現地で選ぶ良さも、SNSなどで探す楽しさも、どちらにもそれぞれの魅力があります。自分の暮らしやタイミングに合った方法で、ぜひ気に入った一枚を探してみてくださいね。