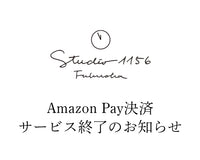窯変(ようへん)とは、陶磁器を焼成する際、窯の中で炎や温度、酸素量などの条件が不規則に変化することで、釉薬や素地の色・質感・形に予期しない変化が生じる現象、またはその効果を指します。作り手も窯を開けてみないと分からないものです。
この現象によって、同じ釉薬や形でも、一点ごとに異なる色合いや模様、風合いが生まれます。こうした偶然性がもたらす個性や温かみは、作品に深みと魅力を与え、特に茶陶や芸術性の高い作品では「景色」として高く評価されます。
有田焼のような磁器は、素地に含まれる不純物が少なく焼成温度も高いため、自然発生的な窯変は起こりにくい性質があります。加えて、江戸時代以降は輸出用として均一な品質が求められたため、偶然性の高い自然窯変は敬遠される傾向があったと考えられます。
ただし、磁器でも「油滴天目」や「辰砂」釉薬を施し、「狙った窯変」に仕上げる作品などはもちろん存在します。