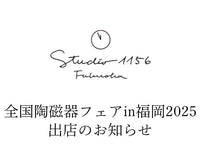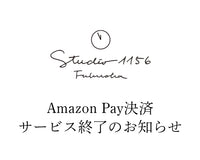油滴天目(ゆてきてんもく)とは、黒釉の茶碗に油を垂らしたような斑点模様が現れるのが特徴の釉薬 、またはその釉薬をかけた天目茶碗を指します。斑文の様子が油の滴のように見えることからこの名がつきました。
有田では、湯呑み・鉢・徳利などにこの釉(うわぐすり)を施した作品も「油滴天目」と呼んでいます。
ただやはり広義では、南宋時代(12〜13世紀)に中国南部の建窯で作られた、釉面に美しい油滴模様をもつ天目茶碗を指します。これらは日本にも舶来し、茶道具として珍重されました。豊富秀吉は、茶の湯を政権運営の重要な道具として使い、唐物(中国渡来の高級茶道具)を非常に重視しました。その中に南宋時代の中国・建窯で作られた油滴天目茶碗も含まれていました。
天目茶碗は、その美しさだけでなく、歴史や文化的な背景も深く、茶道の世界で重要な役割を果たしています。