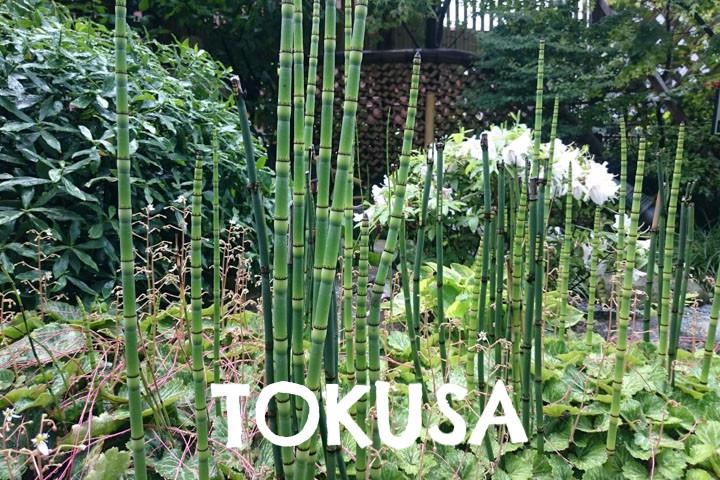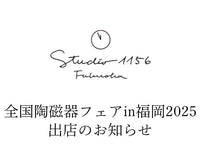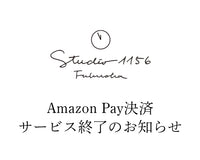読みもの

祥瑞(しょんずい)とは
捻花(ねじりばな)や窓絵などによりいくつかに区分し、その中に毘沙門亀甲(びしゃもんきっこう)や青海波(せいがいは)などの連続模様があり、いずれも縁起の良い象徴として知られています。
陶磁器(とうじき)とは
陶磁器(とうじき)とは、陶器や磁器など、粘土や陶石を成形し焼成した製品の総称です。
陶工(とうこう)とは
陶器や磁器製品を制作する熟練の職人、または作家のこと。
コバルト(こばると)とは
コバルト(こばると)は、染付(そめつけ)に用いられる呉須(ごす)の主成分となる化学元素で、有田焼をはじめ多くの染付作品で発色材として欠かせない存在です。
窯変(ようへん)とは
窯変(ようへん)とは、陶磁器を焼成する際、窯の中で炎や温度、酸素量などの条件が不規則に変化することで、釉薬や素地の色・質感・形に予期しない変化が生じる現象、またはその効果を指します。
うーたん通り(うーたんどおり)とは
うーたん通り(うーたんどおり)とは、有田町の上有田駅南側に広がる中樽(なかだる)エリアの愛称です。